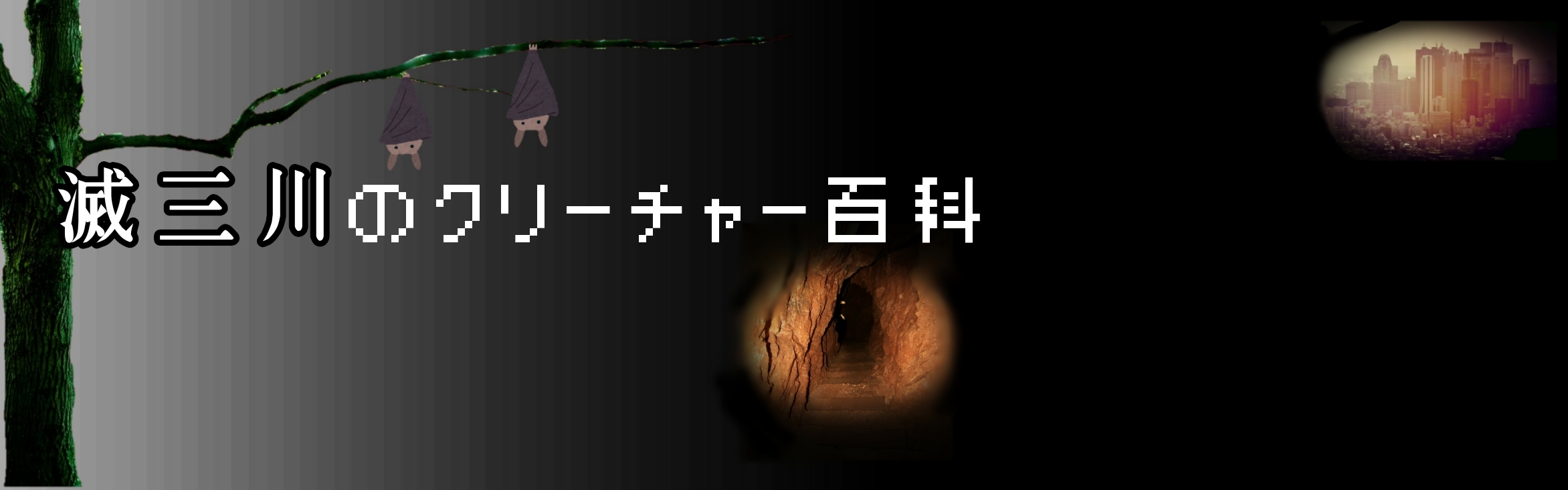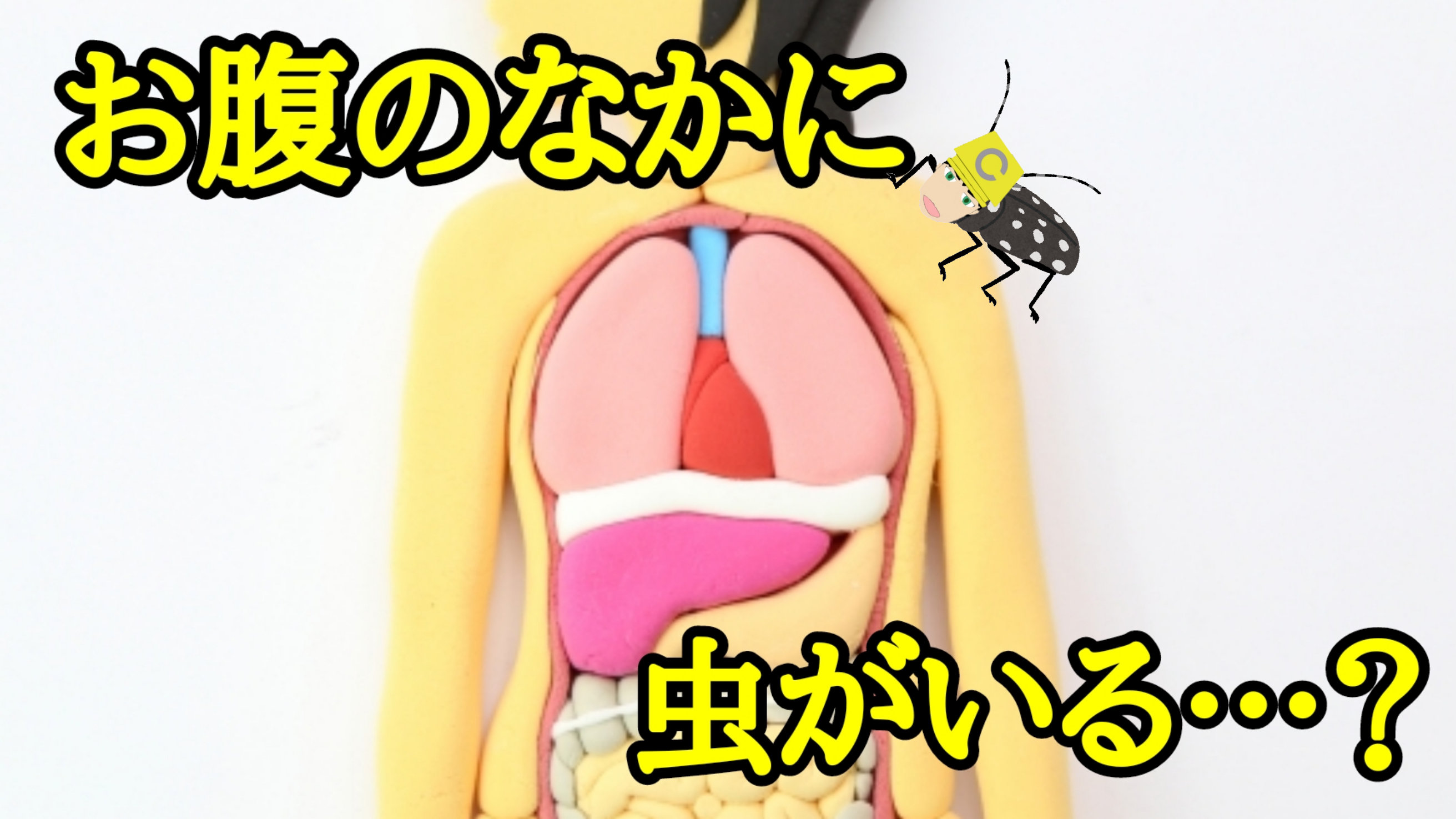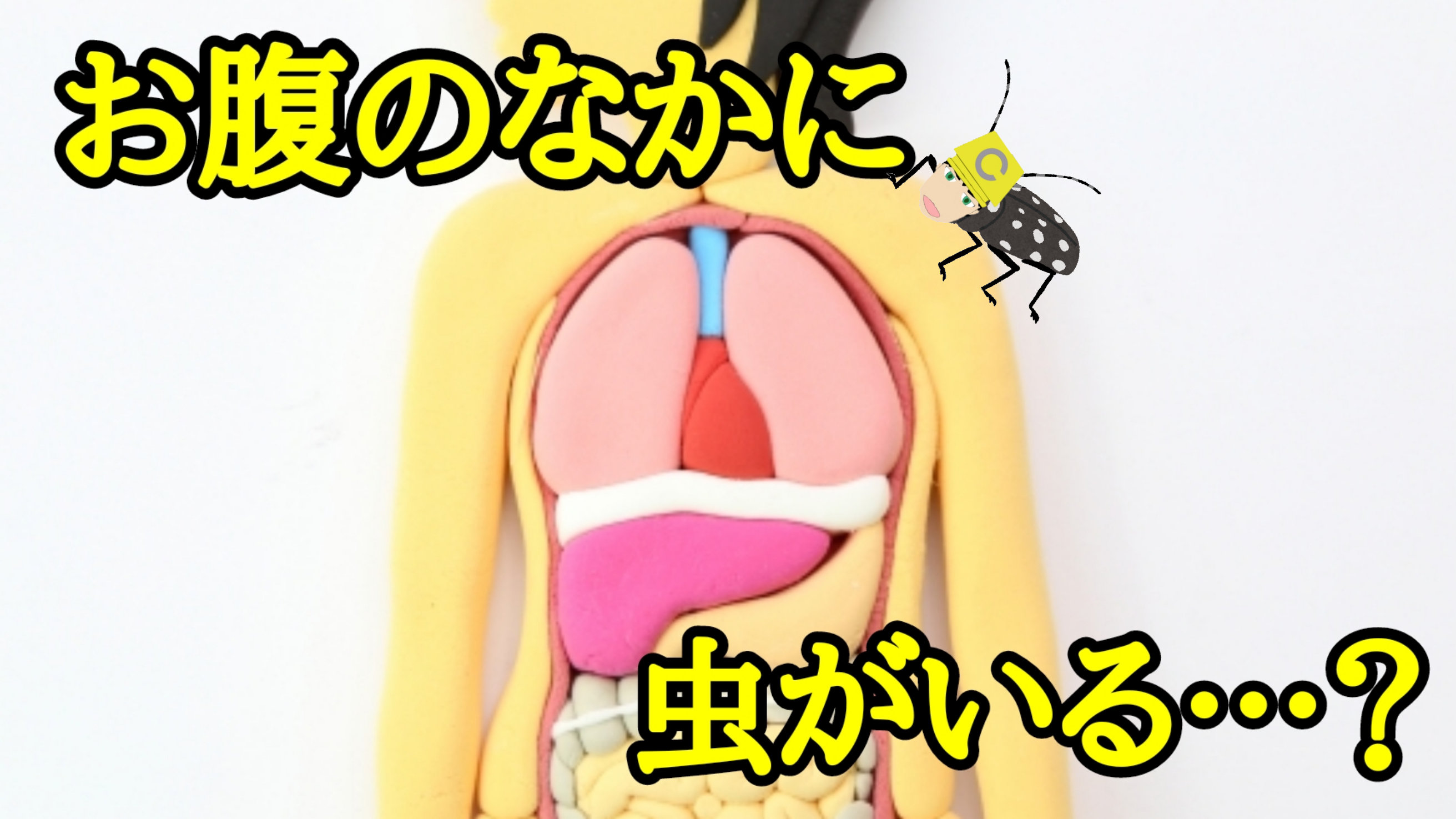
どうも、滅三川です。
動物の持つ武器の中でもっとも人を殺しているものは一説によると「牙」でも「爪」でも「巨体」でもなく「毒」だそうですよ。外からではなく中に働きかける……
幻想生物、妖怪達にもこういったモノ達が存在します。
『ハラノムシ』もそのひとつ。
これは戦国時代の医術書『針聞書』にて紹介されているクリーチャーで人体に潜み悪さをする幻想寄生虫です。
たくさんの種類がいるのですが、動画の方ではアニメに登場した虫達だけを紹介しました。
こちらでは、アニメ関係なしに個人的なオススメハラノムシを紹介していこうと思います。
導入 三尸としょうけらと蟯虫
かつて中国では体内には「三尸九虫」がいるとされました。
まあ、「小さな生き物?がいっぱいいて、色んな悪さをするよ」みたいな話です。
虫の数や性質については様々な説がありますが、後世の日本にも大きな影響を与えたもののひとつに「庚申」の話があります。
『雲笈七籤』や『抱朴子』では、三尸は自分が寄生している人が死ぬと外の世界に解放されるため宿主の早死にを望んでいるとされています。
そして、そんな三尸は庚申の夜、体から抜け出し天に上り、その宿主が行った悪事を告げ口して寿命を縮めようとするのです……
そのため、庚申の夜は一晩中徹夜をしないといけません。これを守庚申とか庚申待ちとか言います。
やがて日本にもこの風習が入ってきまして、そして変化していきます。
まず、ひとつは「三尸」から離れたこと。
「庚申待ち」という信仰形態が独り歩きし、三尸を逃がさないという意味を少し外れて対象の神仏に祈りを捧げるようになりました。
次に新たな妖怪の出現です。
妖怪が好きな人は「悪さを告げ口する」と聞いてなにかを思い浮かべた人もいるでしょう。そう、『しょうけら』ですね。
コイツも庚申待ちのときに悪さをする妖怪で、三尸と同じものと考えられています。『三尸』が日本での読み方、落丁、訛りなどを繰り返して『しょうけら』へと独自の進化を遂げたんですね。
しょうけらの名前は後の絵巻でも見られ、そのイメージからか今ではなんとなく「体内から」というより外から見張っている人に近い妖怪のようなイメージに変化しているようです。
しかし、腹に住むムシの伝承は消えませんでした。
戦国時代の鍼灸師系の医術書『針聞書』は、最初に話した三尸九虫の考え方のような「様々なワルい虫達が体内に寄生する」という事を教えてくれる書物です。
特に、針聞書に記されたハラノムシのうちの一種『蟯虫』は動画の方でもお話ししたとおり「庚申の夜、エンマ様に悪事の告げ口をする」という守庚申の考え方をしっかり継いだ虫だと言えるでしょう。
1 小姓
不気味な姿ですね~。コイツに小姓と名前をつけた人はかなり中二病的なセンスを持っています。
また、不気味なのは姿だけではありません。この虫はアレコレくっちゃべるそうです。妖怪感がすごい……
もちろんうるさいだけでなく、ハラノムシの1種なので取り憑いた人を病にしてしまいます。
しかし、治療のためにこの虫を退治しようとしてもこの虫は薬も針も届かないような所に潜むので不可能、不治の病なのです。
晋の君主、景公はコイツが原因の病によって死んだとも言われています。
曰く、景公が病に倒れている時、夢の中に二人の子供が出てきたそうな。一人が「医者に退治されちゃう」と心配すると「膏の上、肓の下に隠れちゃえばどうしようもないだろ」と答えたそうです。
これが故事成語『病膏肓に入る』の由来です。
2 陽の亀積
取り憑いた人が食べたものを腹の中で横取りしてしまう虫。
そんな虫はとっとと退治したいのですが、よく食べる虫のくせして薬だけは頭の笠ではじいてしまうそうな……なので、ちょっと面白い退治方法を使います。
まずは患者に野豆を食べさせます。野豆は食べ物なので亀積は何も考えずに横取りします。すると亀積は頭の笠を取っちゃうのだとか。
これは、青いさやから取り出した過去を持つ野豆を食べることで、色や形や役割の似た頭の笠も影響を受けて剥かれてしまうからです。
これはヒトガタを模した藁人形に釘を打ち付けて憎い奴を呪ってしまう『丑の刻参り』と同じような類感呪術の考え方による治療法ですね。
3 クツチ虫
ハラノムシは病をもたらす虫なので、現在でも知られている病気の原因と考えられていたであろう者もいます。
「クツチ」とは精神疾患、主に「てんかん」の意味。つまり、コイツに取り憑かれた場合今で言う「てんかん」におかされてしまうのです。
当時はてんかんの治療法が確立していなかったため、やはりこの虫の退治方法は載っていないようです。
また、てんかんではなくてもハラノムシの仲間にはこのように精神に悪影響を与えたり人の意識を奪ったりする奴らも複数います。
4 虫袋
これは、全ての人が生まれつき持っているとされる体内の「袋」です。
不穏なその名の通り、その中には数多くの虫達が入っています。やがてそこから多種多様なハラノムシが生まれ出て、悪さをするのだとか……
この虫袋自体は先天性のものでどうしようもないので、虫が成長する前に退治をすることで大きな病になるのを予防していたそうです。
5 九虫
いよいよ大詰め、ラスボスです。
「三尸九虫」とはさっきも書いたようにたくさんの虫達の総称ではありますが、針聞書では1つの項目としても記されています。
とは言っても一匹の虫ではなく仏教思想に基づいた五色、すなわち白、黒、赤、青、黄のたくさんの虫達の塊です。
もちろんコイツら一匹一匹が怖い病魔ハラノムシです。おっかない……
以上、ハラノムシの紹介でした。
様々な病の原因がこんな不可思議なクリーチャー達の仕業なんだと考えるとなかなか楽しくないですか?
ハラノムシはまだまだいろんな種類がいるので興味があれば書籍や博物館で調べてみるのも面白いですよ。
では