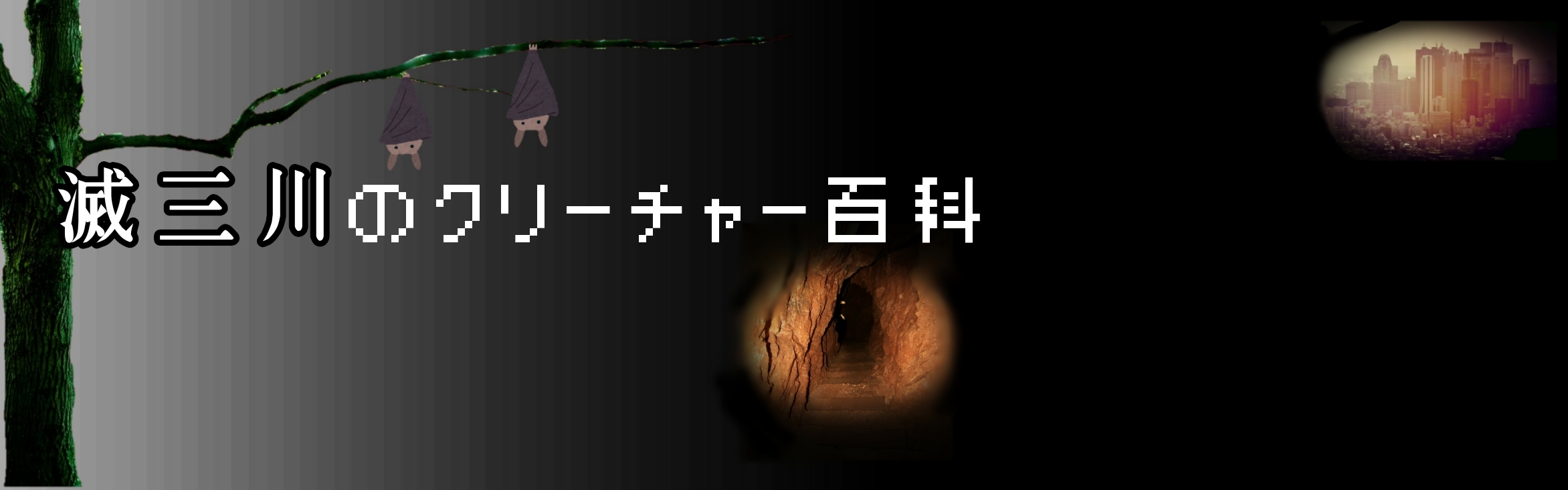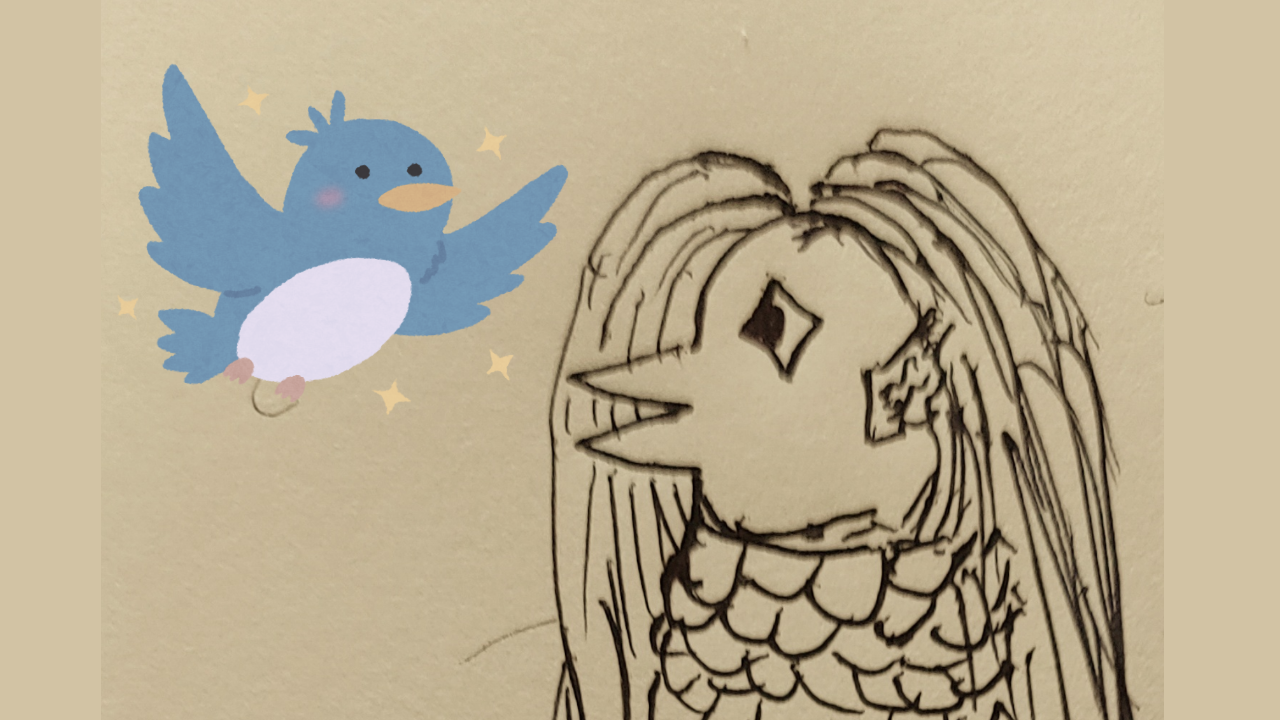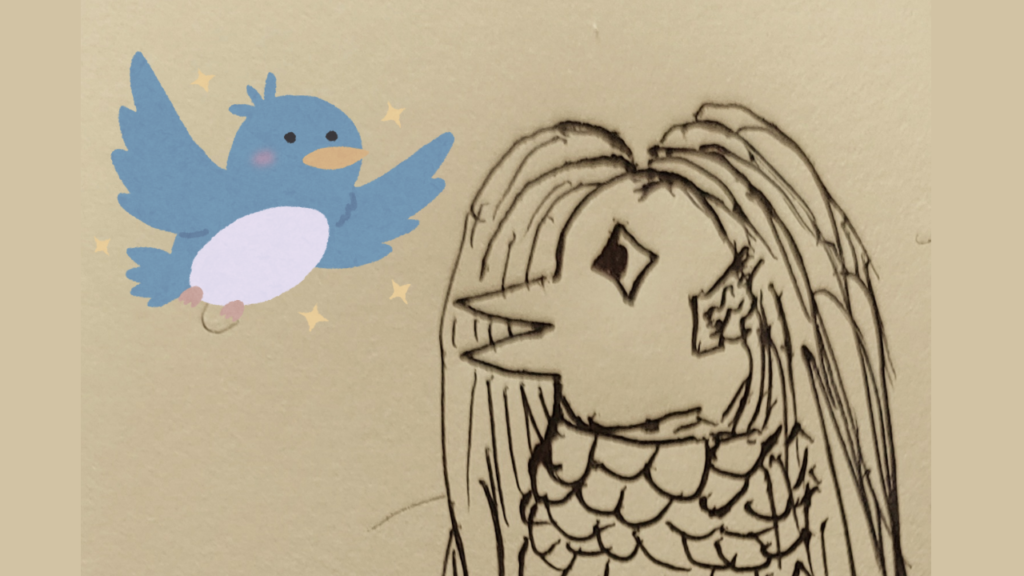
どうも 滅三川です。今日は前回に続いて、アマビエについて語っていこうかなと思います。
今回のテーマは、「なぜ、この時代にアマビエが流行ったか?」です。科学が発達して、さらに言えばどちらかと言えば妖怪より幽霊のほうがまだ信じられているこの時代に、なぜ妖怪のブームが起きたのか、というところを考察していきます。
「 ありがたみ」と 「見た目」と「文化」の3点から探っていきますね。
最初は「ありがたみ」の観点から。
アマビエは「ありがたい存在」だから流行ったとはいえない?
まず、はじめに前提として理解してほしいのが、妖怪が流行ることと妖怪を信じる人が多いことは全くの別物だということです。
現に、江戸時代はその前の時代に比べ、妖怪のイラストが描かれることが多く、妖怪ブームと呼ばれる時期もありましたが、そのブームはおもしろおかしさや楽しさを求めているものも多く、決しておどろおどろしい、こわい、不思議だというスタンスばかりで書かれているわけではありません。
これはある意味、妖怪をほどよく信じていなかったからこそだと思われます。
さて、現代に話を戻しましょうか。 たしかにアマビエブームは起きたものの、大抵の人はアマビエ自体の存在を信じきっているわけではないし、お守りほどのありがたみすら感じていない人もいるように感じられますよね?
きっと実際そうなんですよ。なら、それほどありがたみのない存在がここまで流行った理由は、もっと現実的なところに隠されているはずです。
では、次は見た目に着目して考えていきましょうか。
アマビエはそのシュールさが流行のきっかけ?
そのキラキラしててどこかシュールさが漂うその見た目が、古風で和風な「妖怪」という言葉や、予言とご利益というイメージからかけ離れている、このギャップ感がやはりバズる要因のひとつだったと思われます。
実は、Twitterで妖怪がバズることってこれ以外にもたまにあって、例えば「うまづら」という妖怪が有名になっておりました。まあ、これはコラ画像、つまりウソのネタがバズってたんですけどね。
内容としては昼寝をしていると、顔面が馬で体が人間の妖怪、うまづらが入ってきて、
毛布をかけてくれたり
蚊取り線香をたいたり
緑のカーテン(植物が日光を遮るやつ)をつくってくるたり、
また起きる時間にあわせて口から晩御飯の良い匂いを出し心地よく起こしてくれて、
実際においしい晩御飯も用意してあり、
なおかつそれを食べると出世する、という話。
良い妖怪はたまにいるものの、ここまで現実的かつ至れり尽くせりな話はシュールだし、妖怪のイメージとのギャップもあります。
まあ、ギャップもなにも、この「うまづら」の話に関しては全部ウソの伝承なんですけど……
ただやっぱり、こうしたシュールさのあるおもしろみやギャップというのは火が着くと大きくバズるということがわかりますね。
しかし、このうまづらはただのひとつのバズツイート、つまりひとつのツイートがバズったにすぎません。
もちろんそれに触発されたイラストなどはでてきたきもしますが、それが大きなムーブメントになることはなかったように思われます。
それなら、アマビエも、内容のおもしろみだけではここまで大きな影響は、生まなかったはずです。
そこで、最後に文化について考えていきます。
アマビエと報道文化
前回もちらっと話した、予言獣と かわら版の文化の話をちょっと深掘りしていきましょうか。
前回を聞いていない人のために説明しますと、予言獣とは予言する化け物のことです。
かつて「化け物が不幸な予言をし、自分の姿を写すなり見るなりすることでそれが防げるとつげる」というスタンスの妖怪話が、アマビエも含めて、たくさん存在しており、一種の定番ネタのようになっていました。
ただ、「なにものかが不幸な予言をし、対処法を告げるという話」自体は、実はそういった、アマビエ風の話が出てくる前からすでにたくさん存在しているんです。
そもそも、大昔の政治なんて、なにか珍しいことや不幸なことをなにかが起きる予兆だと理解し、神様からのお告げをもらおうとしていたこともあるわけですし、もっと「予言獣」というニュアンスに近いものだと、馬がある時人の言葉を話し、病気の予言とその予防法を伝えたという話もあります。
ただ、この話でいう予防法は普通の健康法で、自分の姿を写したり見たりすることではないわけです。
では、なぜ「姿を写し書いたら守られる」という種類の話が広まったのかというと、それがズバリ瓦版文化、もっと言えば活字、転写の文化の影響だと考えられています。
「姿を写せば守られる」タイプの話が流行したのは、19世紀なんですが、この時期は文書を転写して広めるということが地方でも全国的に一般化した時代だったんですよ。
もちろん転写して広めているのは知識人層ですが「写しとる、書き写す、」ということが全国で行われている世界になったわけですね。
「姿を写せば守られる」タイプの妖怪の資料には、基本的に姿のイメージ図が載っています。これは、文書として残すことを想定したお話だということです。
これを踏まえて考えると、 知識人達が、ニュース、かわら版を書き写すことができる世界になったからこそ、「姿を写して人に見せろ」というお告げが定番になったといえるんですね。
さて、しかし時代がうつり、アマビエやアマビコといった予言獣は定番ではなくなりました。
ブームや一時の「定番ネタ」が廃れるのは当たり前かもしれませんが、予言獣文化は書き写す文化があったからこそのブームだったと考えると、今までより広い範囲の大衆に情報を届けられるメディア、「マス」メディアがどんどん成長し、情報の流れも加速し、誰も書き写すことがなくなっていったからこそ今までは再興しなかった「定番ネタ」だったのかもしれません。
個人がメディアになった現代、予言獣ネタが復活!
それでは現代に舞台を戻します。現代、たしかにニュースを転写、アナログにペンと紙で書き写してそれを人に見せる機会こそ少ないままですが、ここ数年?十数年?で大きな変化がありました。
それはsnsの誕生と一般化です。
気軽に個人が発信したり、その発信をさらに人に伝えることができるメディアです。文字の情報だけでなく、イラストも載せることができますね。
そこで大きなインパクトを与えているのはトレンドというもので、なにかが話題になったら、システムとしてさらに個人個人にその情報が広まり、またその個人も言いたいことがあればボタンひとつで発信したりするわけです。
これは、ある意味、出版する文化、ニュースを転写する文化、つまりアマビエ達予言獣が定番になった時代の文化が、ついに知識人やマスメディアの手から完全に離れて広がったとも言えます。
そうです、誰もが簡単に情報を伝えることができる時代になったからこそ、情報発信文化と非常に強く結びついている予言獣アマビエがブームとなったと考えられるわけです。
まとめると、 アマビエは別に信じられているから流行ったわけではなく、そのシュールさ、面白さから話題になり、さらに個人が情報発信できる現代だからこそみんながこぞってアマビエを書き写し、大きなブームを生んだ、という話でした。 いやあ、面白い話ですねー。 それではまた今度!