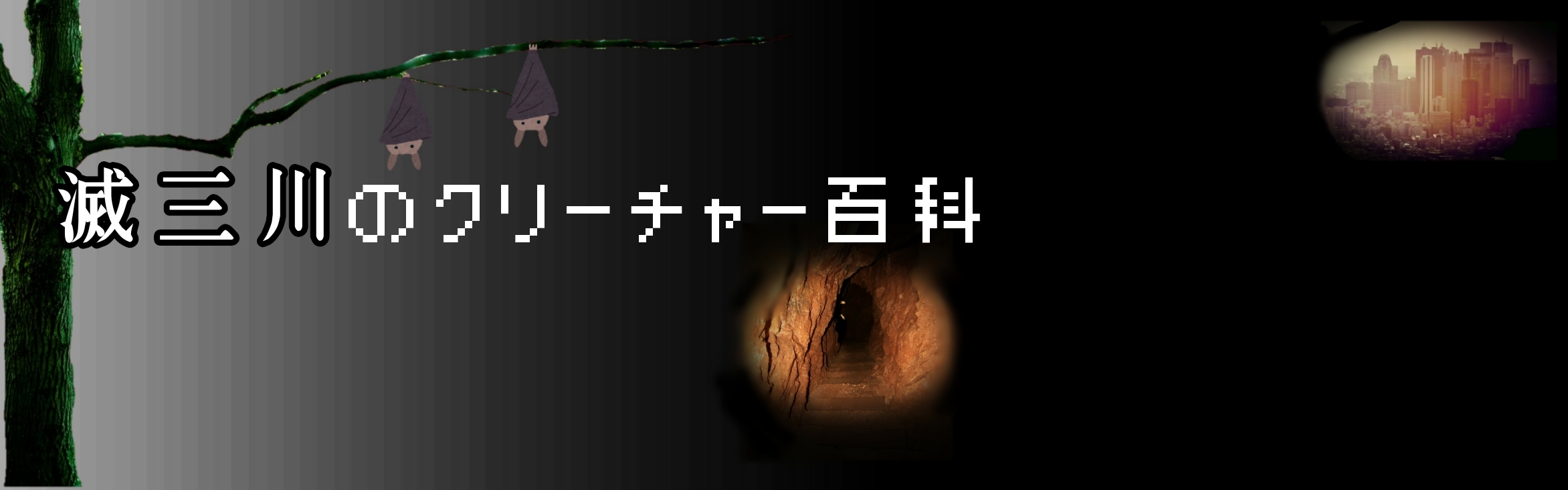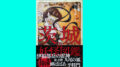河童といえば日本で知らぬものはいない妖怪の代表格です。しかし、この河童というクリーチャー、知れば知るほど奥が深いものです。
というのも「河童伝承」という物は日本全国各地に存在するため地域によって呼び名や生態にブレがあり、「河童とはこういうもの!」と言い切ることが難しいのです。これはつまり各地に伝わる河童的な妖怪を「河童」と一纏めに呼んでいるという話でもありますね。
そんなわけなので、河童と呼ばれている妖怪達の中にも河童のイメージとはかけ離れた伝承をもつ者も多くいるのです。今回はそんなあまり知られていないタイプの河童系妖怪話を紹介していきます。
ヒョウスボ

宮崎県で伝承される河童の仲間、ヒョウスボは水、陸、空を渡る河童です。
春はよく知られた河童と同じように川で生活しているのですが、秋になると山に移って暮らします。そして、この川から山へ移動する時が面白いんです。
「ひょうひょう」と鳴き声をあげながらなんと群れで空を飛んで行くのです。きっと壮観でしょうねぇ。
ちなみに、このひょうひょうという鳴き声が名の由来とも言われますが「兵主神」との関わりについても指摘されています。このような「河童の呼び名」の話もまたいつかしましょう。
ガワイロ
岐阜県に伝わる河童系妖怪です。頭に皿を乗せ時おり相撲を取りたがるような一見典型的(?)な河童です。
しかしコイツのユニークな所は人間狩りの方法です。単純に力ずくで足を引っ張るのではありません。
実はこのガワイロ、頭の皿に特殊な毒が入っており、それを川の中に入れるととたんに水がドロドロになってしまいます。その近くで泳いでいた人はやはり溺れてしまいます。コイツは薬品をを使って人を殺す科学的なハンターなのです。
……また、現実的な話をしますと、川や海などの水中は、ついさっきまで泳げていてもとたんに性質を変えて人を溺れさせてしまうことがままあります。水流や水量、足場の関係等々の影響ですね。
事故を防ぐためには、「安全圏の近くだろうと危険とされる場所には入らない、危険な時間には入らない」などなど、「地域の経験知」をしっかり守らないと「毒」の餌食になってしまいますねぇ。
ワロドン
鹿児島県に伝わるワロドンは、ヒョウスボと同じく秋は山で暮らすタイプの河童系妖怪です。というより、山にいる状態の事をワロドンと呼んでいます。このワロドンはなかなかに生命力のあるクリーチャーです。
なんと、どれだけ体を細切れにされても体の部品が全部残っていれば、元通り復活してしまうのです!
ただ、逆に言えば一部でも体が欠けていれば復活を阻止できるので、切り取った体の一部を犬に食わせれば良いともいいます。アニメや特撮でも自己修復できる敵の対処法としてたまに見かけますよね。
また、おそらく体の大きさを自在に変えられるのでしょうか、馬の蹄の跡に溜まった小さな水溜まりの中にでも何千匹も潜むことができるそうです。(天狗にも似たような逸話がありますがそれはまたいずれ……)
ちなみにワロドンが潜む水は、濁り犬が恐れて逃げていくそうです。それは食べないんだ……
蜘蛛
河童もお化けなので(?)実は何かに「化ける」こともあります。特に長野県や滋賀県などに伝わるお話に興味深いものがあります。
話によると、その地域の河童は虫の蜘蛛に化けるようです。苦手な人はそれだけで嫌かもしれませんが、しかしこの河童、単に姿を変えて驚かすだけではありません。
なんと、狩場の近くにいる人の足に蜘蛛の糸をくくりつけて、それを水の中から引っ張ることで人を溺れさせようとするのです。形を真似るだけではなく能力までコピーできるという事でしょうか……
ただ、人間側も負けてはいません。ある人が足に仕掛けられた糸に気付き、一旦外して木にくくりつけ直したました。河童蜘蛛はそれに気付かず糸を思い切り引きます。すると、なんと木が引っこ抜かれてついには川の中に引き込まれたそうな。さすが相撲で負け知らずの剛力で有名な河童といったところですが、知恵比べでは今回は人間に軍配があがったようですね。
カワコ
河童もお化けなので(2回目)人に「憑く」こともあります。特にこのカワコのエピソードはユニークです。
ある男が何かが川に飛び込む音を聞いたので「カワコだ!」と思い、石を川に投げつけました。
その晩、男は外の見回りに出ていたのですが、足に違和感をおぼえます。ただ、とくに対処もせずそのまま家に帰って寝てしまいました。
すると次の日、自分の腹に梅干し大のデキモノが出来ていることに気づきます。そしてさらにはそのデキモノをつまもうとすると、なんと動き回って逃げるのです!
男は昨日のカワコの仕業だと気付き工具のキリで刺してしまおうと考え、嫌がる家族からキリを奪い取りなんとかそのデキモノを貫くことに成功すると
「キュー」
という鳴き声を最後にデキモノはなくなったとか。
不気味かつ痛~い話ですが鳴き声だけはかわいいという……
一般的な河童なんて存在しない
さて、今回は河童話のなかでも広くは知られていないお話を紹介していきました。しかし、逆に言っておきますと一般的な河童なんてものは存在しません。言い方を変えると「河童ならこんな伝承があるはずだ」という断言はできないということです。
あなたの地元に伝わる河童が人に取り憑く河童であっても、向こうの川の河童はそうじゃないかもしれません。
なんでこんな事を言うかというと、自分の思う河童像をよそに押し付けることで悲しむ人や壊れる文化もあるからなんです。
例えば遠野の河童は基本赤い肌をしていますが、緑の河童がいるんだと言う外の人が増えればかつての「遠野の河童」は薄れ、やがてその地域のアイデンティティーや誇りが傷つけられてしまうでしょう。
また、かつては「河童」と呼ばれていなかった妖怪のことを河童と呼ばれ、傷付いている人もいました。
これはまさしく河童ハラスメント、カパハラです!
河童などの伝承される妖怪達は本来、日本各地それぞれ独立した場所で語られてきたバラエティー豊かな存在です。ひとつの同じ伝承や物語が全国をめぐっていく事を考えても、不確かな人の口を通し、その土地土地を舞台に語られることで、その地域だけのクリーチャーになっていくでしょう。
その事を考えると、似た性質を持つからといって画一的なラベル貼りをするのはあまり優しくありません。
今回はあまり河童と呼ばれない妖怪や、逆に独立した呼び名のない河童蜘蛛の話もしてみました。この記事のように「河童」とされてしまう妖怪にも本来は様々なタイプの妖怪達がいるんだということを覚えておいてあげてくださいね。きっと、あなたの近所の河の住人さんも喜んでくれるでしょう。
……
…
ちなみに、聞き齧った河童のウンチクが全ての河童に当てはまると勘違いして他人にマウントを取ろうとする人には鬼太郎版の水虎が襲いかかります。