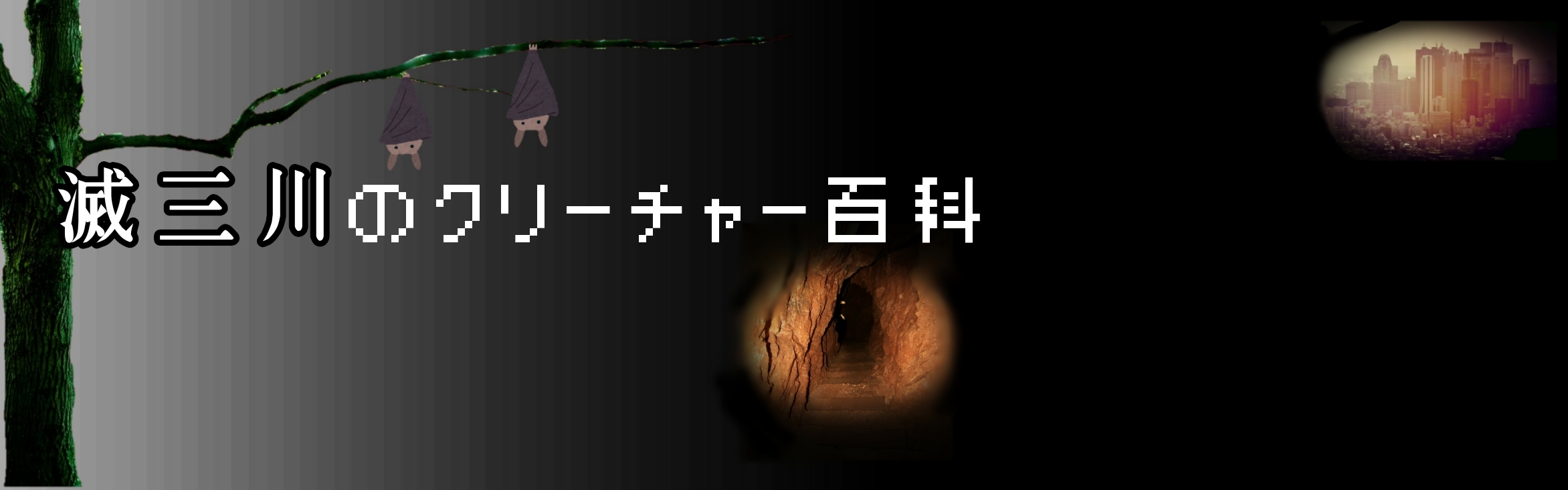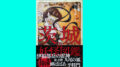どうも、滅三川です。
私はhimalayaという音声配信アプリでもクリーチャーのお話をしているのですが、今回からそこで放送した内容をこのブログで活字としても読めるようにしました!
さて、最初はちょっと前大流行して、ちょくちょくメディアで取り上げられてる妖怪、「アマビエ」のお話でもしていきましょうか。サンプル画像張っておきますね。

「アマビエのご利益はウソなのか」と「この時代に流行ったワケ」の3つの話をしていきます。
では今日は、アマビエのご利益について。
この妖怪はもともと「その姿を描き写すと感染症を防ぐご利益のある妖怪」ということで主にTwitterでバズりました。
ただ、最近では「原典、元ネタには疫病を防ぐご利益について書かれてない!」という指摘もみられるようになっています。では実際のところどうなんでしょうか?
私の情報が古くなければ、「アマビエ」が登場する文献は一つしかないためそれが完全な元ネタとなるので、その内容を現代語で紹介します。これは瓦版、今で言う新聞のようなものの一つの記事ですね。
以下、意訳。
かつて肥後の国の海に、毎晩光るものがでるようになりました。そこで役人が見に行ったところ、その光るものがやはり出現します。そして、その光る怪物は「私は海の中に住むアマビエと申すものだ。今後6年間は豊作になる、しかし病気が流行してしまうだろう。私の姿を写して人々に見せるがよい」と言ってまた海中に消えて言ったそうです。
これが記事本文で、この文の横に今バズっている例のアマビエの挿し絵が描かれています。
さて、この内容を聞く限り、たしかにアマビエは自身の姿を写すように言っただけで、それにより病気から守られるという話は出てきてません。それではやっぱりご利益の話は、原典に忠実じゃない勝手な独自解釈なんでしょうか?
実はそこでご利益は無いと考えるほうが非論理的な考え方なんですよ。
原典に書いてあること、書いてないことを調べることだけが文系学問なんじゃなくて、その資料が書かれた背景や周辺文化のことを調べることこそ重要だったりするわけです。
ここでのキーワードは「瓦版」です。
昔、江戸時代から明治時代、現代で言うところの新聞文化が生まれていきました。研究者達が、当時の資料を集めて、調査していったなかで、今とは少し違う文化もあったことが分かっています。そういった文化のひとつが「予言獣」です。
これはその名の通り、予言をするクリーチャーのことで、当時の新聞のひとつの定番ネタのようなものでした。
定番なので、ある程度内容にも型があって、主に「怪物が現れる、そいつが不幸な予言をする、最後に自分の姿を見たり、写せば予防できると告げる」というのが一連の流れです。
こうした予言獣には、下半身が蛇になっている女性の神社姫や、人面動物のクタベ、三本足の妖怪、アマビコなどの種類がいます。
さて、ここで言いたいのはアマビエの記事が世の中に出てきた時代は「予言する化け物が自分の姿を描き写せというということは、それによって災いから逃れられるという意味なんだ」ということがなんとなく知られている社会だったということです。
つまり、アマビエ自体の資料には病気予防の記述こそないものの、たくさんある類似した内容の記事のことを考えれば、当然アマビエの記事も病気を予防してくれるという意図で書かれた
ものだと考えるほうが妥当、自然というわけなんですね。
例えば、YouTuberが「高評価よろしくお願いします」といえば、普通はグッドボタンを押してという意味だとYouTubeを見ている現代人は分かるし、私が「Twitterもやってるのでフォローしてください」と言ったらあなたは「フォローする」ボタンを押してフォロワーになってくれと言ってるんだと理解できるはずです。
YouTubeやTwitterの文化やシステムを知っている人なら、YouTubeで高評価を頼まれて動画を見た感想を3000文字の感想文にして評価しようとする人も、Twitterをやっている人を慰めるフォローしてくれる人、Twitterを伸ばす協力や助言をしてフォローしてくる人はいないわけです。
だから別に具体的に説明しないわけです。
まとめると「アマビエの原典にはご利益について書かれていないから実際はどういう内容だったかわからない」というのは、当時の定番を知らない我々だからこその誤解で、当時の周辺文化や妖怪のことを研究したところ、実際はご利益があるという内容だったと考えるほうが妥当という話なんですね。
さて、次回は「アマビエがこの時代に流行ったワケ」について考察していきますので、よかったらまた見に来てください、では!